歴史文化講座

東京講座
- [基調講演]
熊倉 功夫氏(MIHO MUSEUM館長)
「利休と秀吉が創造した茶の湯」
- [トークセッション]
-
ロバート キャンベル氏(日本文学研究者)
小堀 宗実氏(遠州茶道宗家十三世家元)
熊倉 功夫氏
「日本人の生活に根ざす『茶の湯』」
歴史文化講座

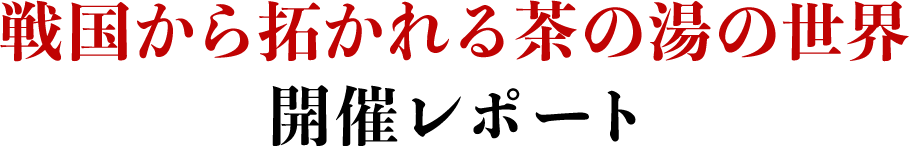
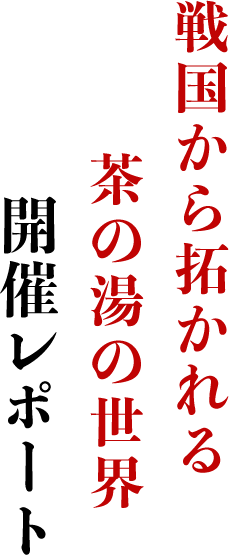
東京講座
熊倉 功夫氏(MIHO MUSEUM館長)
「利休と秀吉が創造した茶の湯」
ロバート キャンベル氏(日本文学研究者)
小堀 宗実氏(遠州茶道宗家十三世家元)
熊倉 功夫氏
「日本人の生活に根ざす『茶の湯』」

1943年東京生まれ。東京教育大学卒業。筑波大学教授、国立民族学博物館教授、林原美術館館長、静岡文化芸術大学学長などを歴任する。ふじのくに茶の都ミュージアム館長。専門は日本文化史、茶道史など。和食のユネスコ無形文化遺産登録の際の検討会会長を務める。主な著書に『熊倉功夫著作集(全7巻)』(思文閣)、『日本人のこころの言葉 千利休』(創元社)、『日本料理文化史 懐石を中心に』(講談社学術文庫)、『茶の湯 わび茶の心とかたち』(中公文庫)、『茶道四祖伝書』(中央公論新社)など多数。

ニューヨーク市出身。専門は江戸・明治時代の文学、特に江戸中期から明治の漢文学、芸術、思想などに関する研究を行う。テレビでMCやニュース・コメンテーターを務め、新聞雑誌の連載、ラジオ番組など、さまざまなメディアで活躍。茶道裏千家の機関誌『淡交』で「ロバート キャンベルの名品に会いに行く」を連載中。主な著書に『東京百年物語』(岩波文庫)、『井上陽水英訳詞集』(講談社)、『日本古典と感染症』(編・角川ソフィア文庫)などがある。東京大学名誉教授。早稲田大学特命教授。

1956年生まれ。学習院大学卒業後、大徳寺派桂徳禅院で禅寺修行を積む。2000年大徳寺管長福富雪底老師より「不傳庵」「宗実」の号を授かる。2001年元旦、13世家元を継承。「茶の湯を通して心を豊かに」をモットーに世界中で文化交流活動を行う。2019年外務大臣表彰、2020年文化庁長官表彰。主な著書に『茶の湯の不思議』(NHK出版)、『日本の五感』(KADOKAWA)、『茶の湯と日本人と』(幻冬舎)などがある。また、新しい試みとしてonline Sado『不傳庵宗実の温茶会』を続々配信中。
CLOSE
茶の湯に高い精神性を見出し、総合芸術へと高めた千利休。その新しい美意識は、パンデミックという「破壊の季節」を迎えた現代に何を問いかけるのか。
この講演会では、MIHO MUSEUM館長の熊倉功夫先生の基調講演、そして日本文学研究者のロバートキャンベル先生と、遠州茶道宗家十三世家元の小堀宗実先生をお迎えしたトークセッションをお届けし、利休の茶の湯と、これからの茶の湯についてお話しいただきました。茶の湯と俳諧の意外な関係や、ホスピタリティと「おもてなし」の違いなど、議論はおおいに深まりました。
当日の模様をご紹介します。

熊倉 功夫(くまくら いさお)
MIHO MUSEUM館長

ロバート キャンベル
日本文学研究者

小堀 宗実(こぼり そうじつ)
遠州茶道宗家十三世家元

大阪の池田市にある逸翁(いつおう)美術館に、豊臣秀吉の姿を描いた絵が残っています。重要文化財ですが、実はこれは下書きで、完成品ではありません。この段階で秀吉に見せたところ「貴意(きい)にて候」————秀吉が「これいいよ」と言った、と但し書きにあり、つまり本人がよく似ていると言ったために大変貴重な画像となりました。日本人の平均身長150センチから153センチぐらいと言われる中で秀吉は猿のように小さかったと言いますから、だいたい140センチぐらい。本当に小さかった。
次に千利休です。利休が亡くなってから長谷川等伯が描いた千利休像は、堂々たる顔つき、堂々たる体躯です。実は利休がもらったという甲冑が表千家から出てきました。修理して、14代家元の而妙斎(じみょうさい)宗匠が試しにそれを着てみたら、ちょうどよかった。而妙斎宗匠はだいたい165センチぐらいです。今なら中肉中背ですけれども、当時の165センチは相当の偉丈夫。利休は大男だったんですね。
当時のいろんな記録の中にも、利休は大男だと書かれています。その大きな利休の前に、140センチの秀吉。身長差が25センチ。秀吉からすると相当威圧感がありますね。ですから、初めは仲間だと思っていたのにだんだん大男が気に食わなくなってきて、最後に切腹を命じたのではないか、と思えるぐらい、2人には体格上の問題があったようにも思います。

利休が作り上げた茶の湯とはどんなものだったのでしょう。利休が作ったといわれるもので確かなものの一つが「待庵(たいあん)」という茶室です。山崎の妙喜庵(みょうきあん)というお寺の中にあって、たった2畳です。秀吉が座ると、利休と秀吉の距離感は、だいたい1メートルあるかないか。いや、もっと狭い。そういうところで利休がお点前して、秀吉がお茶を飲むわけです。利休はこのとき初めて、躙口(にじりぐち)という小さな出入り口を作りました。だいたい66センチですから、人の出入りを拒否するような入り口です。ここにやっぱり利休の思惑があるのでしょう。全国に茅の輪(ちのわ)くぐりという神事がありますが、6月30日に神社などの社頭に茅で作った輪が置かれ、それをくぐればこれからの暑い夏を無病息災で過ごすことができる、と言われます。小さな口をくぐり抜けると浄化され、人間が生まれ変わる、という深層心理があるのでしょう。茶室についても、外は俗界だけれど、躙口をくぐった中は清浄の世界で、浄められた人間でなければ入れない空間。こういうものを作ったのが利休なのです。
次に壁です。壁土が落ちないようにつなぎの繊維を入れるのですが、普通はその上から上等な細かい土で上塗りをしてきれいにします。ところが待庵の壁は上塗りせず、藁が見えるまま。荒壁であることが美しい、という感覚ですね。框(かまち)も丸太のままです。本来、座敷の框は角にきちっと削るものです。今でこそ和風住宅には丸太材をたくさん使いますが、その出発点がこの待庵なのです。
利休はさらに、茶室に向かう途中に手水鉢(ちょうずばち)を設けました。本来、神社仏閣の入り口で穢れが境内に入らないように心身を清めるものですが、茶室にも俗世間のさまざまな穢れを茶室に持ち込んではいけないということで手水鉢が茶の湯の庭にも置かれるようになったのです。しかも、手水鉢はしゃがみこんで使う、つまり這いつくばうから「つくばい」と言います。躙口でもつくばいでも、人はしゃがみ込むというわびた姿を見せることになります。利休は茶の湯での「ふるまい方」も示したのです。
利休はどんな茶碗を作ったか。樂長次郎作の「大黒(おおぐろ)」という茶碗があります。特徴は、立ち上がりがすっとして、高台は丸く削られていて、低い。真っ黒です。何もない。どこにも作為がないように見えます。作為はあるのですが、隠されている。いかにも自然な姿。一切の装飾性を拒否した、こんな茶碗を利休は注文したのです。
次は釜です。お湯を沸かすための釜は大昔からいくらでもありますが、茶の湯のために初めからデザインされた釜が作られました。「阿弥陀堂」という釜は利休が型紙に作り、与次郎という釜師が作りました。その試作品ができたとき、まだ幼かった利休の孫の宗旦が、このとき利休が与次郎に指示した言葉を覚えていました。「肌をかつかつと荒らし候へ」。形は利休のデザイン通りだけれど、「もっとガリガリッと粗くしてくれ」と言ったのです。そんな肌合いが利休さんの望むところだったようです。
次に花入です。利休以前には竹の花入れはありませんでした。利休の作った竹の花入で「園城寺(おんじょうじ)」というものがあります。園城寺、つまり三井寺(みいでら)の釣り鐘は大きなひび割れがありますが、この花入れもひび割れがあるので、鐘のひびに見立ててこの銘を付けたのです。「桂籠(かつらかご)」という花入れも、もともとは桂川の漁師が捕った魚を入れておくための籠です。「あ、これは花入になるじゃないか」と言って利休が使った。これが見立てです。本来どう使われているか、ではなくて、自分がそれを持ったらどう使おうか、それが見立てです。
利休のもう一つの美の創造に「破壊」があります。もうできあがったものを壊してしまうのです。しかし利休のこのような方法は、周りの人から見ると危なっかしくてしょうがない。弟子の山上宗二が「利休という人は、山を谷、西を東と言いなして、茶の湯の法度を破る」と書いています。みんなが西というところを東と言い、山と言うところを谷だと言う。世の中の常識と正反対のことを平気でやる人だと。「茶の湯の法度を破りて自由にする」……これが利休の生き方であり、戦国がそういう時代でした。常識や階級というものを壊して、新しいパラダイムを作り出したのです。
そのような時代の波に乗って出てきたのが秀吉であり、その秀吉のよきパートナーが利休でした。秀吉はこの天才的な演出家、美の創造者を120%利用するわけです。秀吉の時代の政治は、劇場化していました。人々の目を引くようなことが政治スタイルの一つになります。安定期には天皇も将軍も隠れて見えませんが、激動期には権力者が民衆の前に姿を現します。その「権力者登場の場」を作ったのが演出家としての利休でした。
秀吉をセレモニーの主人公にするには、どういう場を作るか。利休は秀吉のために黄金の茶室を作りました。これはポータブルで、九州の名護屋城でも京都でも、あちこちで使われています。天正13年に秀吉が正親町天皇にお茶を差し上げる禁裏茶会も利休の演出でした。宮中での茶会はこれが最初で最後です。
もう一つはイベント。つまり大衆を動員した北野大茶の湯です。天正15年10月1日に北野の松原で開かれたお茶会は、800席が作られたと言います。北野の社殿の真ん中に利休と津田宗及、今井宗久、そして秀吉がそれぞれ茶席を設け、そこでお茶を飲むためのくじ引きまでありました。それこそ空前絶後。
秀吉は茶の湯というものを一つの政治文化にしました。そこに利休と秀吉の接点があったわけです。おかげでお茶は日本を代表する大文化になりました。
秀吉が「こんなことやりたい」と言えば、利休は思いがけないアイデアをどんどん出し、それを秀吉が楽しむ。利休からすると、秀吉の蔵の茶道具をわが物顔に使えます。2人は蜜月でした。お互いに許し合う関係だったと思います。それが壊れ始めるのが天正15年。秀吉が島津を征伐してほぼ全国を制覇すると、その恩賞を自分の配下に与えるために新しい領地を求め、朝鮮半島に目を付けます。そうすると、その前線基地である九州博多の商人・神屋宗湛(かみやそうたん)が秀吉にとって非常に重要な人物になってきました。堺を基盤とする利休の地盤沈下です。
加えて、下剋上の時代が終わりました。秀吉からすると次に下剋上を起こったら自分がひっくり返されます。その芽を摘むために、秀吉は太閤検地や刀狩りなどをして、新しい中央集権的な政権を目指しました。その体制では、利休のような下剋上的な茶の湯も邪魔になります。天正17年12月、利休が大徳寺山門の修理を完成した記念に利休の木像を山門上に置いたところ、利休を排斥しようとする人たちが問題視します。勅使や秀吉も通る門の上に、利休が雪駄履きで立っているのは不敬ではないか、と。これがいよいよ政治問題化するのが天正19年の正月。利休は一気に突き落とされるような状況に置かれます。
そして2月、利休は「切腹せよ」という命令を秀吉から受けました。利休は死を前にして自分の心境を四字四行にまとめる遺偈(ゆいげ)を記します。「人生七十、力圍希咄(りきいきとつ)、吾這寶剣(わがこのほうけん)、祖佛共殺(そぶつぐせつ)」。人生70年、もうすべきことを全部したと。この宝剣を持って一切合切を切り捨てて、無の世界に行こう。「堤る我得具足の一太刀(ひっさぐるわがえしぐそくのひとたち」、私が持っているこの宝剣すらも「今此時ぞ天に抛(いまこのときぞてんになげうつ)」、今は放り出してしまおう。
利休はどこかでまだ戦えると思っていたのかもしれません。最後のお茶会には徳川家康を呼んでいます。秀吉に対抗できる唯一の人物です。でも、それももういらない、と。遺偈を書いた3日後、2月28日に切腹して亡くなります。
秀吉と利休という天才と天才がぶつかったとき、何が起こるか。パトロンとアーティスト。パトロネージがなければ芸術というのは発現できませんが、芸術家は必ずしもパトロンの意のままになるわけじゃない。そこで深い溝ができて悲劇に至る。これは世界の美術史でいくつも見られるテーマです。そのように見ると、秀吉と利休の結末は、なるべくしてなったように思われるのです。


熊倉先生

小堀先生

熊倉先生

小堀先生

キャンベル先生

熊倉先生

小堀先生


キャンベル先生

熊倉先生

キャンベル先生

小堀先生

熊倉先生

キャンベル先生

熊倉先生

小堀先生

熊倉先生


熊倉先生

キャンベル先生

熊倉先生

キャンベル先生

熊倉先生

キャンベル先生

小堀先生

熊倉先生

小堀先生

キャンベル先生

小堀先生

熊倉先生

キャンベル先生


熊倉先生

小堀先生

熊倉先生

キャンベル先生

熊倉先生

小堀先生

熊倉先生
※写真はイメージです。