
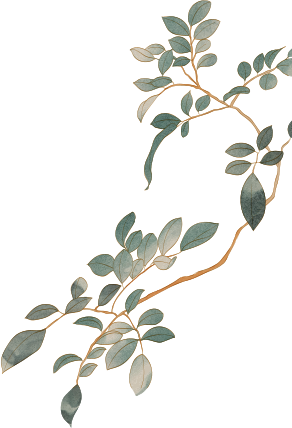
石清水八幡宮
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に描かれる激動の時代を京都に見つけます。

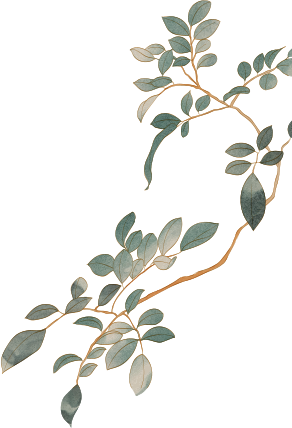
石清水八幡宮

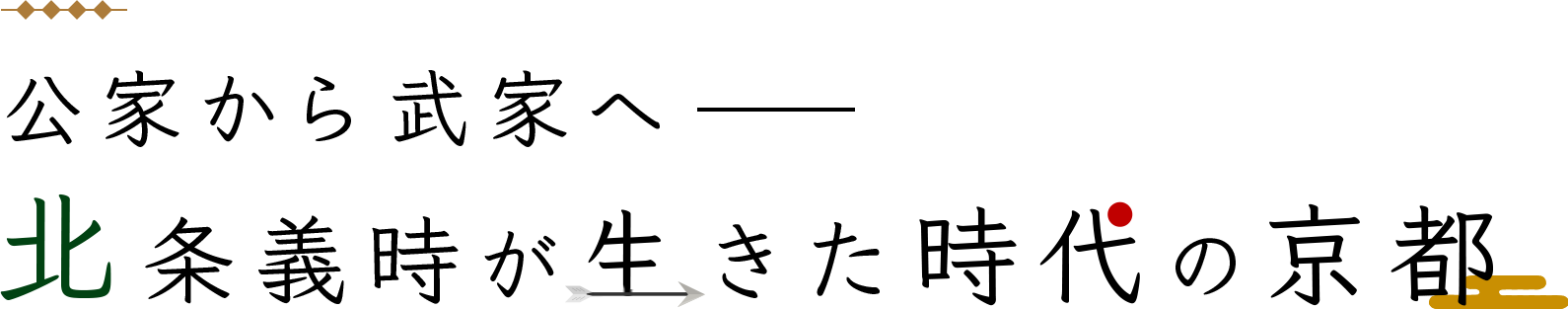
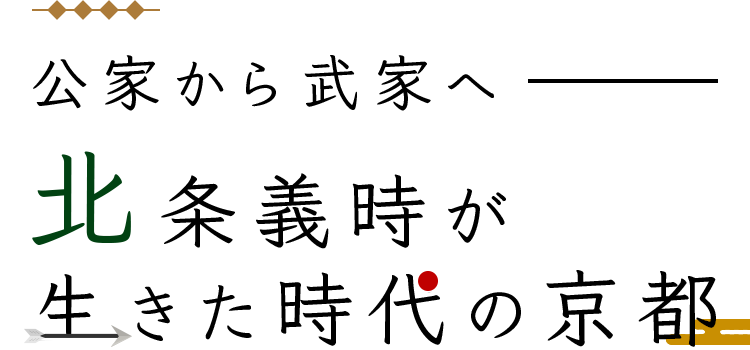
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に描かれる激動の時代を京都に見つけます。
2022年の大河ドラマは
主人公の北条義時が
義時は新しい権力「鎌倉方」に
華やかな王朝文化を
激動期の京都を、
今回は、源平の争乱の発端となる「以仁王(もちひとおう)の令旨」を発した
後白河法皇の皇子・以仁王の足跡をご紹介します。

 提供:妙法院
提供:妙法院保元元年(1156)、貴族たちによって長く政治が行われていた京の都で、初めていくさが起こりました。朝廷内の権力闘争は平安約350年のうちで幾度もありましたが、このとき「武力」が用いられたことで「武士」がどんどん力を増していきます。そんな中で生まれたのが平清盛(たいらのきよもり)。武家出身ながら政治権力を掌握し、新しい国作りに邁進します。朝廷を牛耳っていた後白河法皇(ごしらかわほうおう)にも心遣いを忘れず、清盛は莫大な資産を投じて法皇に蓮華王院(れんげおういん・三十三間堂)を寄進しました。鎌倉時代に火災に遭いましたがまもなく復興され、南北120メートルものお堂や本尊の千手観音坐像、そして壮観の千体千手観音立像などが国宝に指定されています。
スポット情報

平家を全盛に導いた清盛ですが、大きなミステイクをしていました。保元に続いて起こった平治の乱で源義朝(みなもとのよしとも)を討ち取った際に、三男の頼朝(よりとも)の命は奪わず、伊豆へ流すだけにしました。このため、頼朝は伊豆の在地領主、北条時政(ほうじょうときまさ)のもとで力を蓄え、以仁王が発した平家追討の令旨を受けとると兵を挙げることになります。ここに源平の争乱の幕が開けました。
しかし令旨を出した以仁王自身は、即座に平家に追われる身となりました。奈良へ逃げる途中、宇治川で追いつかれ、大激戦が始まります。『平家物語』に描かれる、最初の宇治川の合戦です。

 ©平等院
©平等院以仁王に平家追討をささやいたのは、源氏の長老として平家政権下に身を置いていた源頼政です。彼の率いる兵が宇治川で平家に応戦しました。以仁王は平等院でつかの間の休息をとって奈良へと逃れていきますが、源頼政は深手を追い、平等院の内で自害しました。これほど激しい戦いがあったのにも関わらず、鳳凰堂が創建時の姿のままで現在に残されているのは、極楽浄土に見立てられたお堂の周りを池が取り囲んでいたためと言われます。
平等院は永承7年(1052)に関白・藤原頼通によって別荘を寺院に作り替えたもので、当時隆盛した浄土教の思想から、この世に阿弥陀仏の極楽浄土を作り出しました。「極楽いぶかしくば宇治の御寺をうやまへ」──極楽は本当にあるのかしら、と疑うなら、宇治の平等院にお詣りしなさい……しかし交通の要衝である宇治川に接するため、幾度も地獄のような戦乱に巻き込まれました。


以仁王は援軍となってくれるはずの興福寺を目指して南へと馬を走らせていましたが、現在の木津川市綺田(かばた)という場所でついに流れ矢に当たり、落命しました。興福寺の援軍の先陣はもうすぐそこまで来ていたと言われるので、『平家物語』ではその身の不運が嘆かれています。現在も綺田には以仁王の墓が伝えられ、その御霊を祀る高倉神社が地元の人々の崇敬を受けています。
MAP今回は、平家滅亡の立役者である源義経と、側室・静御前の足跡をご紹介します。


平家打倒のために、伊豆で挙兵した源頼朝。勢力を増やして鎌倉入りすると、平清盛は地団駄をふみつつ平維盛を総大将にして兵を東国に送り込みます。「富士川の合戦」となりますが、甲斐源氏の武田信義(たけだのぶよし)と合流していた頼朝の兵は膨れ上がり、平家軍は水鳥の飛び立つ音にすらおののいて退却してしまいました。
その翌日、頼朝の前に一人の若武者が現れます。平治の乱で伊豆に流されたときに生き別れになった弟の義経でした。当時赤子だった義経は鞍馬寺に預けられ、伝承によると昼は仏道修行、夜は僧正ガ谷(そうじょうがだに)で天狗に兵法を授けられたといいます。そのため鞍馬寺には義経の背比べ石や、兵法修行に励んだという木の根道が伝わります。成長した義経は父の仇を討つべく鞍馬寺を出奔し、奥州平泉の藤原秀衡(ふじわらのひでひら)のもとに身を寄せ、兄頼朝の挙兵を聞いてその陣を訪れたのでした。やがて悲劇の運命をたどる義経ですが、その魂は鞍馬寺に還ったと伝えられ、僧正ガ谷の義経堂には遮那王尊として祀られています。
木曽義仲(きそよしなか)も兵をあげ、ついに平家は都を落ちていきます。摂津の一ノ谷に陣を張った平家を追い落とすのは義経。旧山陰道を駆け抜け、鵯越(ひよどりごえ)という奇襲により大勝しました。京都に凱旋したとき、義経は「静御前(しずかごぜん)」という美しい女性と出会います。彼女は当時大流行していた「白拍子(しらびょうし)」という芸能を生業とする人でした。


『平家物語』によると平清盛も祇王(ぎおう)という白拍子を寵愛していました。しかし仏御前(ほとけごぜん)という白拍子に心移りしたため、祇王は妹の祇女(ぎじょ)と母の刀自(とじ)とともに奥嵯峨で尼となります。一方、仏御前も世の無常を感じて清盛邸を飛び出し、祇王のもとで念仏の日々を送りました。
その庵の跡が現在の祇王寺と伝わります。明治初年に廃寺となり、大覚寺門跡の楠玉諦(くすのきぎょくたい)師が復興を願っていたところ、明治28年に元京都府知事の北垣国道(くにみち)氏が祇王祇女の悲話にふれて別荘を寄付しました。それが現在の建物です。仏間に安置される祇王祇女らの木像はその玉眼にやわらかな光をたたえ、苔の庭も樹林のあいまにぼんやりと光り、『平家物語』のしめやかな世界が息づいています。


義経と静御前の出会いは、現在の二条城の南にある神泉苑と言われています。平安京の創建時に自然の池や森林を利用して造られた遊覧の地で、天皇や貴族に愛されていました。一方、さまざまな祈祷が行われる霊場としても知られ、空海による請雨修法や、疫病の原因とされた御霊を鎮める「御霊会(ごりょうえ)」もここで行われました。
『義経記(ぎけいき)』によると、ある年100日間も日照りが続き、名のある高僧たちが神泉苑で祈祷しても効果は無く、龍神への奉納として白拍子100人を呼んで舞を舞わせることになりました。しかし99人舞っても雨の気配がないまま、最後の一人が前に出ました。それが静御前です。途中まで舞ったところで黒い雲が湧き上がり、雨は3日も降り続けたといいます。これを見ていた義経はたちまち静御前に恋をしました。
今なお善女龍王を池の中島にまつり、本堂には天皇ゆかりの聖観音菩薩をまつるなど、真言宗寺院として人々の信仰を集めています。現在は国指定の史跡に指定されています。


奇襲、急襲に長けた義経は、平家を西へ西へと追い詰め、ついに壇ノ浦の海に沈めました。大手柄の義経ですが、頼朝の心はこの弟から離れていきます。頼朝の平家追討の本来の目的は、天皇の正当性を証明する「三種の神器」と安徳天皇を平家から取り返すことでした。ところが義経の猛攻でわずか8歳の安徳天皇と神器の宝剣が永遠に失われる結果となります。また、平家滅亡の立役者となった義経が後白河法皇との距離を縮めたことも頼朝は不満でした。ついに頼朝は義経追討を命じ、義経は追われる身となります。
義経は潜伏していた雪の吉野山で愛する静御前と別れ、奥州へと逃れていきます。一方、静御前は頼朝のいる鎌倉へ連行され、生み落とした義経の子を殺されました。義経もまた平泉の地で自害して果てます。
悲劇のヒロイン、静御前の晩年はさまざまに語られました。その一つに、静御前は生まれ故郷である現在の京丹後市網野町磯(いそ)に戻り、義経と子の菩提を弔う日々を送ったという伝承があります。それゆえに海沿いの高台に静の御霊を祀る静神社があり、海に突き出した崖の上に静御前生誕の地碑が置かれました。日本海の低く垂れ込めた空の下、波音や海鳥たちの声が彼女の魂を癒やしたのでは……と想像してしまう風景です。
今回は、源平の合戦の終焉による信仰の深まりと、権力を掌握した源頼朝の入洛の足跡をご紹介します。


平家が全盛期を迎えていた承安5年(1175)、一人の僧が25年間も止住した比叡山の黒谷を出て、それまでにない新しい教えを説き始めました。僧の名は法然房源空(ほうねんぼうげんくう)。「ただ阿弥陀仏の救済を信じ、その名号を唱えるだけで極楽浄土におもむくことができる」という専修念仏(せんじゅねんぶつ)を説いたのです。折しも武家が台頭して朝廷を圧し、また長い内乱で多くの命が失われ、人々の心は疲弊していました。念仏だけで誰でも救われるという法然の教えは、弱き人、貧しき人にも光明を与えます。なかでも運命的に殺生の罪を背負っていた武士たちは、どれほど心の安寧をもらえたことでしょう。法然の庵には多くの人々が訪れ、その一人一人に法然は浄土のことわりを教え、念仏の行を勧めたといいます。比叡山を下りた法然が初めて庵を結んだ地として伝わるのが金戒光明寺です。殺戮をくりかえした源氏方の武将・熊谷直実も救いを求めてここに法然をたずねたという伝承があります。境内には直実が身に付けていた鎧を池で洗い、それを掛けたという「鎧掛けの松」が植え継がれています。彼がここで「生き直し」を求めたことを今に伝えているのです。
スポット情報

一ノ谷の合戦で源氏方の勝利が決まったころ、熊谷直実はなお猛る功名心を満たすべく、さらなる敵を探していました。そこに現れたのが見事な鎧姿の平家の武将。直実は馬を並べてむんずと組み、波打ち際にどさりと落としてその顔を見ました。薄化粧にお歯黒をほどこした美しい少年は、我が子と同じ16,7歳ほど。思いがけない気品と幼さに直実はとまどいます。しかし背後からは源氏の軍勢が押し寄せ、とうてい助かるまい、と直実はその首をとりました。「ああ、武芸の家に生まれなかったらこんな哀しい想いはしなかったのに」。直実はさめざめ泣いたといいます。首の主は平敦盛。『平家物語』に描かれる名場面の一つです。8年後、直実は武士の身を捨てて出家しました。直接の理由は所領争いが関係しているとされますが、若き敦盛の死を背負い続けていたのは想像に難くありません。法然と出会った直実は「法力房蓮生(ほうりきぼうれんせい)」と名前を変え、浄土宗の普及に邁進します。長岡京市の光明寺は、蓮生が法然ゆかりの地に建立した「念仏三昧院」に始まる寺院です。その名前のとおり、晩年の蓮生は罪を背負ったまま、阿弥陀仏の救済を信じてひたすら念仏に生きたのです。
スポット情報

奥州合戦で奥州藤原氏を討伐した頼朝に、もうその地位を脅かす敵はいませんでした。翌年の建久元年(1190)11月7日、大軍を従えて京都に入ります。頼朝にとって約30年ぶりに目にする都でした。在京中の宿所としたのは、かつて平家が豪壮な居館を並べた六波羅。現在の六波羅蜜寺のある一帯で、平家が都落ちした際に火を放ったために、広大な土地が残されていました。多くの軍勢を留めるのにちょうどよく、また敗者の屋敷跡に頼朝が拠点を築くのは勝利宣言のようなものでした。頼朝は上洛を前に壮大な館を築かせ、この際に敷地内にあった六波羅蜜寺も修繕させたと言われます。頼朝は都に1カ月あまり滞在し、後白河法皇と8回にわたって会見し、日本の軍事・警察権を一手に担うことを取り付けたようです。権大納言や右近衛大将にも任官されますが、都での政務が必要な官職は頼朝にとっては不要で、鎌倉へ帰る前にすべて辞退しています。歴史に名高い「征夷大将軍」に任命されるのは、翌々年、後白河法皇が崩じた後のこと。在京不要の「大将軍」こそ、鎌倉殿・頼朝が望んでいたものでした。
スポット情報

京都滞在中、頼朝は政治的駆け引きのかたわら、都の社寺への参拝も欠かしませんでした。建久6年(1195)の二度目の上洛の理由も、東大寺大仏殿の落慶法要に参加するためでした。平重衡によって焼き払われた東大寺は国家鎮護のシンボルであったため、何よりも復興が急がれていました。後白河法皇が資金を提供して大仏開眼にまで至りましたが、その亡きあとは最高権力者として頼朝は篤い支援を行っています。長い内乱の後、なにより求められたのは亡者たちの鎮魂と、残された人々の心の救済です。頼朝もそれを十分に理解していたと思います。頼朝は2度の上洛において合計5回も石清水八幡宮に参拝しています。平安時代に宇佐八幡宮から勧請されて以来、国家を守護する神として朝廷の篤い崇敬を受けていましたが、清和天皇が創建したことから清和源氏の守護神として武家からの信仰も篤いものでした。特に頼朝の祖先である源義家がここで元服して「八幡太郎義家」を名乗ったころから、源氏の信仰は深まります。北条義時も供奉したという頼朝の度重なる石清水八幡宮への参拝は、武将としてトップに立ったことの報告でもありながら、失われた命への手向けでもあったように思われるのです。
スポット情報今回は、後鳥羽上皇が北条義時追討の兵を挙げて敗れた「承久の乱」の舞台をご紹介します。


洛南の鳥羽は鴨川と桂川が合流するあたりで池沼も多く、その水景を愛でた貴族たちが別荘を営んだ場所です。平安末期になると白河上皇や鳥羽上皇が「鳥羽殿」という離宮を営んで院政の拠点にしました。広大な離宮は都市のように整備され、後鳥羽天皇も19歳で譲位すると鳥羽の地に遊んだと言います。若き上皇は才気あふれるワンマン帝王として朝廷に君臨し、武家の台頭によって陰りつつあった王朝の輝きを取り戻そうとしました。朝廷儀礼の復興や勅撰和歌集の編纂などに取り組み、そんな都の文化に三代将軍・源実朝も憧れを抱いたようです。後鳥羽上皇と実朝の関係はきわめて良好でしたが、その実朝が暗殺されると、鎌倉幕府に対して上皇は不信感を抱き始めます。在京の御家人たちを取り込んで「武力」を増強させ、鳥羽殿にあった「城南寺」に「流鏑馬(やぶさめ)揃い」という射芸を口実として、東は美濃、西は但馬に至る国々から兵を集め、承久3年(1221)5月15日、ついに「北条義時追討の院宣」を出して挙兵します。この城南寺が現在の城南宮のあたりと言われます。挙兵の報を受けた鎌倉幕府は北条政子の名演説で結束を固め、都へと猛攻。後鳥羽上皇方は約1ヵ月で敗北し、上皇はこの鳥羽殿に幽閉されました。ここから配流先の隠岐へと向かったのです。
スポット情報

後鳥羽上皇は挙兵に際して、在京の御家人たちを京方の武将としてスカウトしています。その一人が三浦胤義(たねよし)です。鎌倉幕府の重鎮である三浦義村の弟ですが、京に上って検非違使(けびいし)の宣旨を受けていました。挙兵に際して胤義は鎌倉の兄に手紙を送り、ともに決起することを促します。しかし義村は使者を追い返して北条義時に挙兵のことを伝え、義時に忠義を誓うのです。返事さえもらえなかった胤義は、その後京方として破滅の道を進みます。瀬田川の合戦から敗走した胤義は、どうせ討たれるなら後鳥羽上皇の前で討たれようと御所に駆けつけますが、上皇は戦闘に巻き込まれるのを恐れて、早く立ち去れ、と言い放ちます。絶望した胤義は、それならば京に進撃する兄・義村に討たれようと東寺に立てこもります。この頃の東寺は源頼朝らの支援を受けて多くの寺院を再興した文覚によって修繕されて間もない頃で、今は失われた回廊もぐるりと諸堂を取り囲んでいました。ここから胤義は入京する義村の旗を見つけ、無念の想いを叫びます。しかし義村は「シレ者ニカケ合テ、無益ナリ(愚か者とわたり合っても無駄)」とつぶやいて立ち去るだけでした。
スポット情報

兄の義村にさえ見放された胤義は、東寺を飛び出してさらに鎌倉方と死闘をくりひろげ、西へ向かいました。太秦に屋敷があり、そこに残してきた子どもたちに会うためだったと言います。しかし京方の指揮官であった胤義が敵から逃れることは難しく、ついに「木島(このしま)の里」にある神社で息子の胤連らとともに自害します。ちょうど挙兵から1ヵ月後の6月15日、ここに承久の乱は終わりました。この神社が「蚕ノ社(かいこのやしろ)」の呼び名で知られる木嶋坐天照御魂神社(このしまにますあまてるみたまじんじゃ)です。胤義が自害した際に火が放たれたため社殿は焼失しましたが、すぐに再興されたようで、発掘調査によって鎌倉前期の整地跡が確認されています。嵐電の駅名ともなった「蚕ノ社」という名称は、本殿の東隣にある蚕養(こかい)神社(東本殿)に由来します。この一帯はかつて養蚕や機織りを伝えた渡来系氏族の秦氏の本拠地であったことから秦氏ゆかりのある古社と考えられ、平安時代には祈雨の神として信仰を集めていました。
スポット情報

胤義が自害したその日、六条河原では鎌倉方と後鳥羽院の勅使が対面し、「北条義時追討の院宣」が撤回されました。「私の考えじゃない、臣下たちの企みだった」と言い訳するものの、後鳥羽院は鳥羽殿に幽閉され、やがて隠岐へと流されていきます。「我こそは新島守(にいじまもり)よ隠岐の海の荒き波風こころして吹け」──私こそは新しい島守だ。隠岐の海の荒い波風よ、それをよく心得てやさしく吹いておくれ……波だけでなく荒れ狂う心も、歌を詠むことでなぐさめたように思われます。流罪の身とはいえ、後鳥羽上皇は隠岐で『新古今和歌集』の改訂や『遠島御歌合』を行うなど、大好きな和歌に没頭していたといいます。その死まで帰還は許されませんでしたが、19年もの歳月をこの孤島で過ごせたのは、隠岐の生活が案外快適だったためかもしれません。都には遺骨だけが戻りました。洛北大原の勝林院(一説に西林院)に安置され、後鳥羽上皇の寵妃だった藤原重子(修明門院)が上皇の水無瀬御所の建物を大原に移して法華堂と称し、納骨しました。現在の法華堂は江戸時代の再建で、明治時代に整備された後鳥羽天皇大原陵の傍らに佇んでいます。
MAP